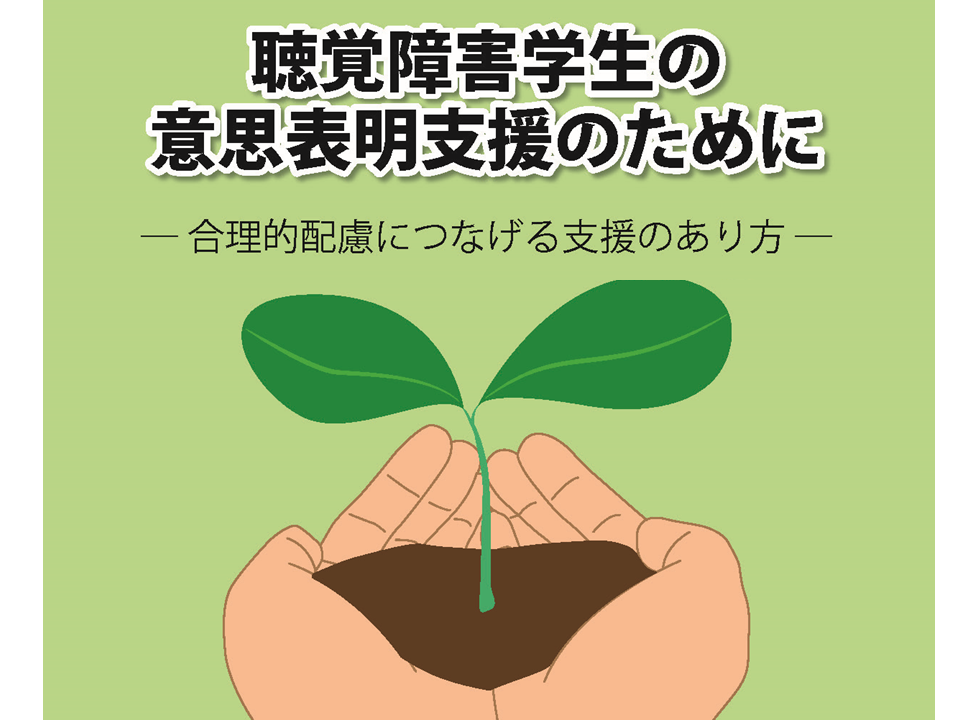1.消極的反応段階での支援

残念ながら、現在の日本では「私は大丈夫です」「支援は必要ありません」と支援を求めない聴覚障害学生が一番多いようです。「特別扱いされたくない」「周りと同じようにやっていきたい」という気持ちがあるからこそ、ここまで来られたとも言えるでしょう。
支援する側が、聴覚障害学生のこれまでの生き方を否定せずに受けとめると同時に、サポートの魅力をいかに伝えていくかが、ポイントになるかもしれません。
支援例 1
A大学では、次年度にはじめて聴覚障害学生が入学してくることがわかりました。
早速、入学後の支援について話し合おうと、教員が本人と面談して必要なサポートを尋ねたところ、「口話でわかりますから、特にサポートは・・・」としっかりした返事がありました。
その場では無理にサポートを勧めずに、「一度、授業を見学してみようか」と見学日を約束するにとどまりました。
後日、実際の授業を目にした聴覚障害学生は、「やはり口話ではわかりません・・・」とサポートの必要性に気づいたようです。今ではノートテイクやパソコンノートテイクを活用して受講しています。
支援例 2
専任の障害学生支援コーディネーターを置いているB大学では、聴覚障害学生が受講する講義のほとんどにノートテイクをつけていますが、ある聴覚障害学生は「私は大丈夫です」と支援をかたくなに拒否しています。
コーディネーターから「一度だけでいいから、ノートテイクをつけてみない?」と勧めたり、聴覚障害の先輩から「ノートテイクっていいよ」と話してもらうように伝えたりと、半ば押し切る形でノートテイクをつけてみました。
当初は困惑した様子でしたが、次第に授業の楽しさに目覚めた模様です。
ここでのポイント
支援例1・2とも、本人の支援を拒否する気持ちを受けとめつつ、「サポートはいりません」という言葉をうのみにせずに、潜在的ニーズを意識した丁寧な対応が功を奏した例と言えます。これまでに一度も通訳を見たことのない、サポートを受けたことのない聴覚障害学生にとっては、サポートは遠い世界のできごとです。サポートを通して初めて知る「世の中にはこんなにも情報があふれていたんだ!」「授業ってこんなに楽しかったんだ!」という感慨は、「障害を人に知られたくない」「人に頼らなくてもやっていける」という不安や気負いをはるかに上回るものなのでしょう。
2.受動的依頼段階での支援

時おり、消極的反応段階を素通りしてスムーズに支援に入っていける聴覚障害学生がいます。
理由を尋ねると「友達もやっているから」という例が目立ちます。
親の会やろう学校、聴覚障害学生組織で知り合った先輩や他大学の同級生が情報保障を利用しているから、自分も、というパターンは心理的に抵抗が少ないようです。
大学に入るまでにこうした同じ聴覚障害の仲間との出会う機会が大切なことを再認識するときです。
支援例 3
数多くの聴覚障害学生が在籍するC大学。
学内に聴覚障害学生のセルフヘルプグループがあり、毎週・毎月ミーティングが持たれています。
通訳について話し合う企画では手厳しい意見も飛び出しますが、さまざまな意見が交わされる中でそれが個人的な問題なのか、聴覚障害に共通した問題なのかが、整理されていく様子です。
大学としても、定期的にセルフヘルプグループと話し合う場を持ち、支援に反映させるようにしています。
支援例 4
障害学生支援室が中心となって聴覚障害学生支援に着手したD大学では、ノートテイクやパソコンノートテイクをつけてのサポートを進めています。
外部から講師を招いての話し合いの席で、聴覚障害学生に近況を聞いたところ、「来年度からゼミが始まるんだ、どうしようかと思って・・・」とため息を漏らしています。
「手話通訳は考えていない?」と水を向けたところ、「エッ、手話通訳つけられるの?!」と驚いています。
結局、地域の派遣センターから手話通訳者を紹介してもらい、新たな支援が進んでいます。
ここでのポイント
学外の学外の機関や団体主催の研修会に参加したり、逆に学外から講師を招いて勉強会を開いたりすると、異なる角度からの視点を得られることがあります。支援例4はその結果、聴覚障害学生の何気ないサインをキャッチして、より効果的なサポートができた例です。この段階では、聴覚障害学生から「○○してほしい」という声があがっていないから大丈夫、と安心しがちな時期ですが、通訳者から「この通訳で本当にいいのかどうか、本人の意見を聞きたい」という声も寄せられているのではないでしょうか。通訳者と本人とを交えて話し合う場を用意すると同時に、通訳者を交えずに話し合う、養成講座の中で実際のノートや通訳を見ながら「この方法はどう?」と具体的に聞くなど、聴覚障害学生の本音を引き出せるような工夫が随所に求められます。
また、支援例3のように、聴覚障害学生同士でサポートに関する意見交換する場が持てる大切さも強調しておきたいところです。大学生の場合には「全日本ろう学生懇談会」などの各団体で、ディスカッションや講演会など様々な企画が行なわれています。また、地域の聴覚障害団体には若手の方が集まる青年部があり、活発に活動している例もありますので、折をみて「こういう企画があるみたいよ」と伝えてもよいでしょう。
全国ろう学生懇談会とは?
全国のろう学生が集まって、交流や学生生活での問題についての話し合い等を行い、学生生活の向上を図っている団体で、関東と東海に支部があります。毎年開催される「全国ろう学生のつどい」では、学生生活についての情報交換や交流会が行われています。

3.主体的活用段階での支援

ここにきて、一方的に支援を受ける段階を脱して、利用者としての意識が芽生えていきます。
「同じ聴覚障害の友達がいる」というところからさらに踏み込んで、支援の内容やあり方について議論を重ねる姿が見られるでしょう。
どちらかと言えば、上級生や大学院に通う聴覚障害学生が多いかもしれません。
支援例 5
ある聴覚障害学生は、E大学大学院に進学するにあたって、より高度な通訳を受けたいと思っていたところ、教員から遠隔通訳の相談がありました。
新しい手段の通訳なので不安はありましたが、教員自らが遠隔通訳に取り組んでいること、専門性の高い通訳者を確保できたことから、乗り出してみることにしました。
講義のたびに、教員、通訳者、聴覚障害学生の3者での反省会があり、忙しい日々ですが、自分もサポートに加わって試行錯誤しているのを実感します。
支援例 6
聴覚障害学生を受け持つF大学のある教員は、4年生になった聴覚障害学生から相談を受けました。「専門講義で手話通訳をつけているけれども、講義中は手話通訳を見ているからノートが取れなくて困っている」というものでした。
当初は教員が自分でパソコンを持ち込んでテイクをしてみましたが、すぐに頓挫しました。
通常のノートテイクは2人体制で行なわれていますが、この講義はノートテイカーを1人配置し、ノートをまとめてもらうようにしています。
ここでのポイント
この段階では、従来の支援にはない新たなサポートを求める学生や、一つの支援に多くを求める学生も現れてきて、大学側も戸惑うところかもしれません。不満が噴出しやすい時期でもありますが、自分の要求を言語化できるようになった証として受けとめていきたいところです。
すべての要求に応じるのが厳しい場合も、「できません」と却下するのではなく、「それは○○という理由で厳しいけれど、こういう方法はどうか」と大学としての代替案を示すことが欠かせないでしょう。お互いの事情をすり合わせて建設的に話し合い、折り合っていく過程は、合理的配慮の決定のために必要なプロセスでもあり、且つ聴覚障害学生にとっても自信となっていくようです。
概してこのような学生は、後輩や通訳者に熱心に関わるようになりますし、後々、サポートを受ける立場から自らサポートを提供する立場に回る人も見られますので、長い目で見守りたいものです。
執筆:関東聴覚障害学生サポートセンター 吉川あゆみ氏
(所属・肩書きは2006年度時点)