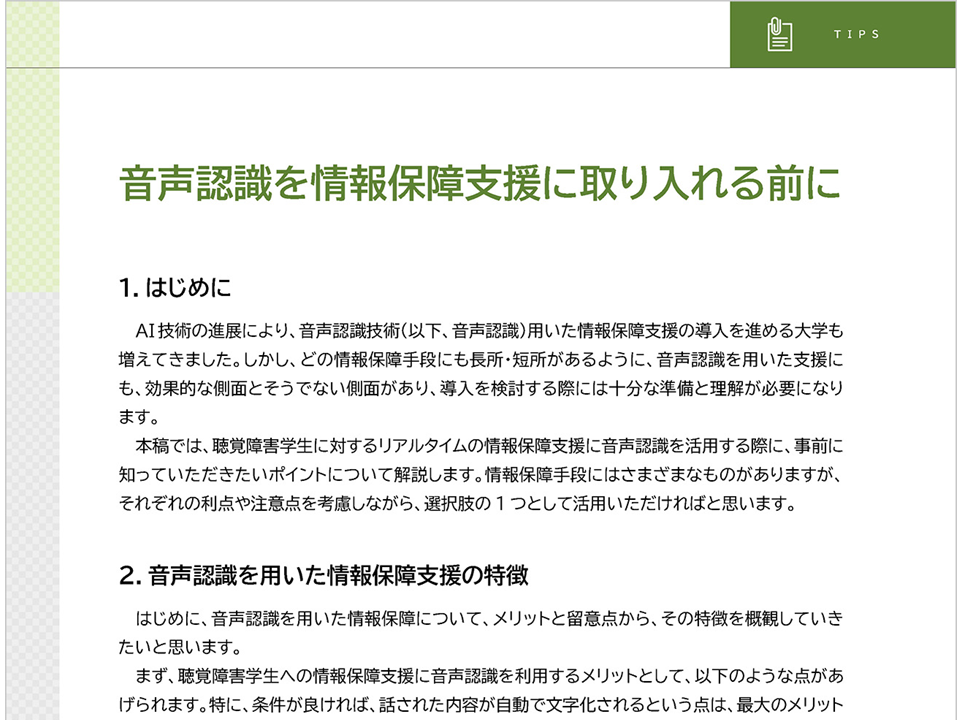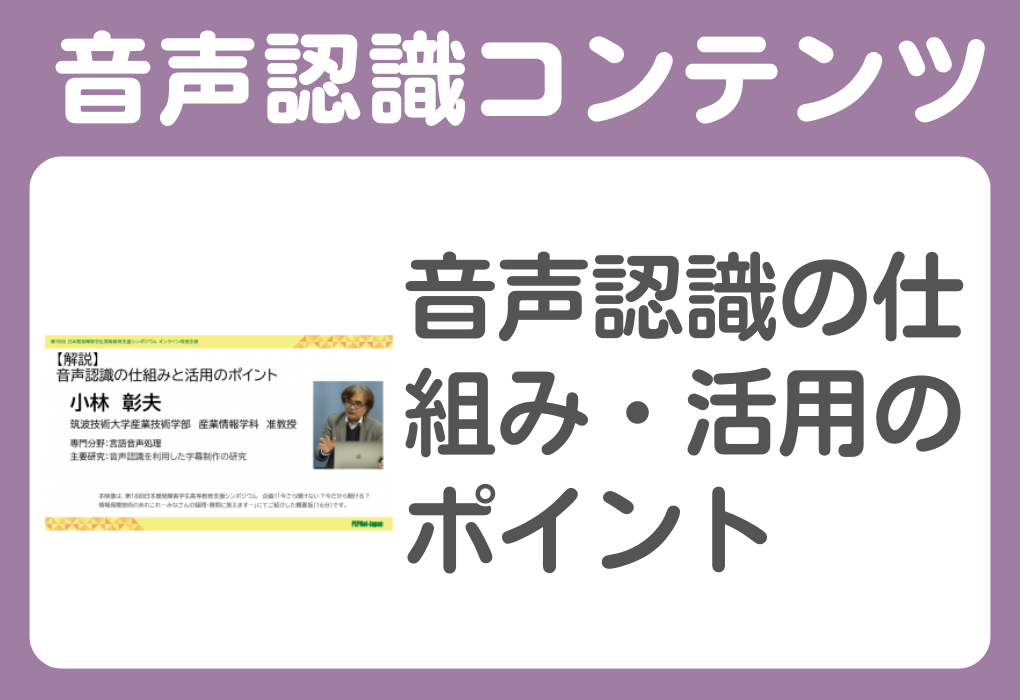2024年10月23日 公開
PEPNet-Japan聴覚障害学生支援のためのナレッジベース内で公開されている「音声認識を情報保障に取り入れる前に」では、音声認識技術を導入する際に知っておくべき基本的なポイントについて説明しました。
音声認識には、話された内容がリアルタイムで文字化され、迅速に情報を共有できるというメリットがあります。
けれども、誤認識のリスクもあり、話者の話し方や環境によって、字幕の質が大きく左右されてしまうため、使用する際には、あらかじめ音声認識の特性をよく理解するとともに、使用場面を見極める必要があることを強調してきました。
このマニュアルでは、こうした留意点を踏まえ、はじめに活用していただきたい「1対1の会話」や「少人数での会話」場面を取り上げ、具体的な活用方法について解説します。
多くの大学では、「授業場面での情報保障に音声認識を利用したい」という目標があると思います。
しかし、上記マニュアルでも述べたように、いきなり授業場面で音声認識を取り入れるのはリスクが伴います。
このため、将来的に授業での活用を考えている大学であっても、まずは対話場面からの活用を始め、音声認識の特性を十分に理解した上で、徐々にステップアップしていっていただければ幸いです。
もくじ
1.はじめに
2.アプリケーションの選定
3.基本的な利用方法
1)1対1での会話
2)複数人での会話
4.その他の活用法
1)パソコンを使って修正したい
2)教室の音響機器とUDトークを接続したい
3)ロジャー製品とUDトークを接続したい
4)トークルームを事前に作成しておきたい(UDコネクト)
5.よくあるトラブルと対処法
1) トラブルシューティング
2) 認識精度を高めるために