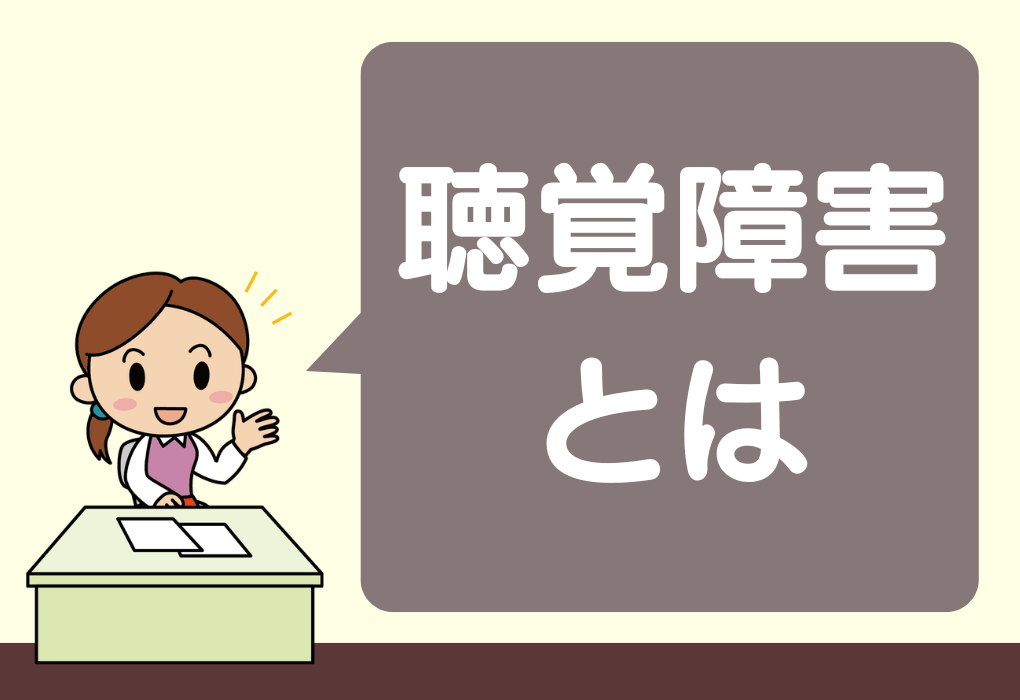聴覚に障害のある学生が大学生活を送る際に、まず問題になるのが授業への参加の方法です。音声がほとんどききとれない学生の場合、大教室で教員が90分間話し続ける講義形式の授業では、まったくと言っていいほど情報が入りません。たとえ補聴器や人工内耳を活用してある程度音声を聞き取れる学生であったとしても、曖昧な音声を90分集中して聞き取り続けながら未知の学問を学ぶことは非常に負担の大きい点を忘れてはならないでしょう。
また、スライドなど、視覚的な情報の提示は、聴覚障害学生にとってとても有効な配慮の一つです。
ただ、この場合であっても、スライドの内容を読むだけの時間になってしまうような状態では、授業に参加する意味が見いだせないこともあるでしょう。大学の授業は、資料や文献から得られる情報のみでなく、先生方の体験に基づいた解説や他の学生の発言など、この場でしか得られない情報があるからこそ、学びにつながるものです。そのため、どのような形態の授業であっても基本的には何らかの形で「情報保障」が必要と考え、有効な手段を検討していく必要があるでしょう。

高校まではどのような支援体制にあったのでしょうか?
聴覚障害学生が高校までに受けてきた支援の内容は、育ってきた教育環境により異なります。聾学校で教育を受けてきた学生の場合、教員が手話を用い、多様な視覚教材を併用しながら、1クラス10人以下の少人数指導を受けてきたケースが多いでしょう。これに対して地域の小学校・中学校・高校では、教員が資料を配付したり、板書やパワーポイントなどの視覚教材を用いたりして指導を行っている例が多いようです。ただ、こうした支援のみでは、十分な情報が伝わっていないことも多く、地域の学校に通っていた聴覚障害学生の多くは「ほとんど独学だった」と語っているなど、決して授業内容がわかる環境にはなっていなかったとみるのが現実的です。
しかし、高校までの授業の場合、内容は教科書にそって進みますし、参考書も豊富に出版されています。また、クラス単位で授業を受けるため、周りの生徒や教員は皆、当該生徒に聴覚障害があるということをわかった上で、何か困ったことがあれば、それなりに手助けをしてくれることも多かったことでしょう。これに対して大学の授業では、教科書を利用する例も少なく、あったとしてもその内容だけ理解しておけばよいというものではありません。また、授業によって参加する学生が異なるため、本人が特に申し出ず、教職員から説明することもない場合、他の受講生は当該学生の聴覚障害について知らないまま授業が進んでしまうことも少なくありません。
本来は高校・大学の区別なく、いずれの教育機関においても適切な支援体制の構築が望まれるものですが、大学は、聴覚障害学生にとってそれまでの学校と大きく環境が異なること、そして授業参加や情報アクセスにあたってさまざまな障壁が生じる環境にあるため、相応の合理的配慮が必要という点を理解いただければ幸いです。
執筆:筑波技術大学障害者高等教育教育研究支援センター 白澤麻弓