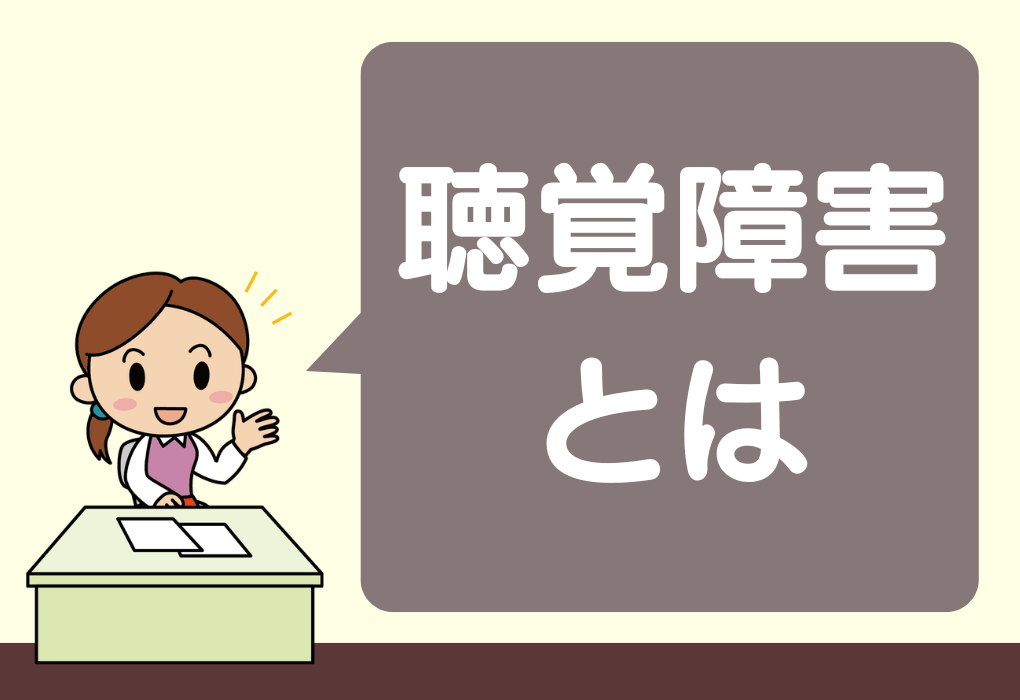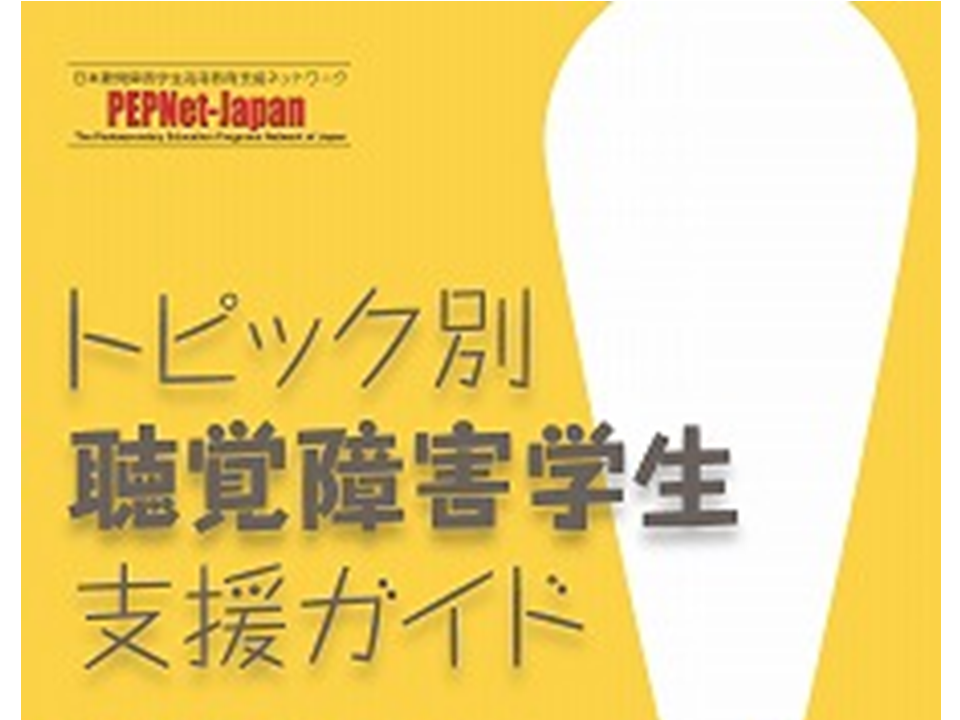聴覚障害学生とコミュニケーションをとる際に用いることができる手段には、口話(こうわ)や筆談、手話などがあります。
口話というのは、口の形を読み取ったり、聞こえてくる音や表情、話の流れから相手の話していることを察知して話をする方法のことで、話をする側は口の形をはっきりあけ、ゆっくり話すなどの配慮が不可欠です。また、表情や身振りを用いたり、通じにくい部分には筆談や空間に文字を書く空書(くうしょ・そらがき)等を併用したりすると、より確実なコミュニケーションをとることができます。
ただ、口話によるコミュニケーションでは、どうしても不確実さが残ってしまうのも事実です。また、複数人の会話を同時に読み取ることはできないので、何人かの教職員とともに会話をしている場面では、ともすると聴覚障害学生のみがその場のコミュニケーションから置き去りにされがちです。そのため、手話を用いる学生に対しては教職員側も少しずつ手話を覚えて使ったり、積極的に筆談を行なうなどして、聴覚障害学生がコミュニケーションに参加できる環境を作っていくことが大切です。
1対1または数名の会話では、音声認識ツールを用いて音声を文字化し、筆談代わりに活用する方法もあります。この場合、音声出話す側も文字化の状況を確認し、誤りがあれば言い直したり訂正したりしながら会話を進めていくことで、安心して会話に参加することができます。

Q.すべての学生が手話を用いるわけではないのですか?
聴覚障害学生が用いているコミュニケーションの手段は、その学生が育ってきた背景によって大きく異なります。
学生の中には、「インテグレーション」といって普通の学校で聞こえる児童・生徒とともに学んできたケースも多く、この場合には大学に入るまで手話に触れる機会がなかったという例も多く見受けられます。また、「聾学校」の中では、幼少期から手話を取り入れている例もあれば、中学部・高等部になってから本格的に導入する例もあり、学校ごとにさまざまです。聾学校に在籍していた期間や、手話を使うコミュニティ(同級生や上級生の人数)の規模などによって、手話の用い方には個人差があると言えるでしょう。
執筆:筑波技術大学障害者高等教育教育研究支援センター 白澤麻弓