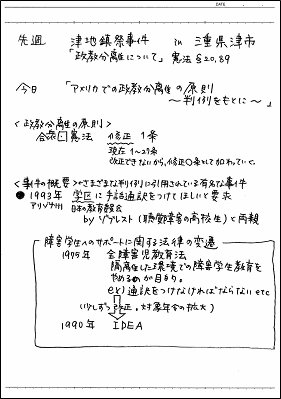【事例1】 -早稲田大学の例-
1.早稲田大学の支援状況
(1)早稲田大学障がい学生支援室とは
早稲田大学に在籍する身体障がい学生(聴覚障害・視覚障害・肢体障害)を全学的に支援するために2006年3月に設置されました。3名の障がい学生支援コーディネーターがいます。
聴覚障がい学生支援に関しては、支援室が募集・養成・コーディネート・フォローを行い、教員との連絡等は各学部を通して行っています。
(2)聴覚障害学生の状況
2006年現在6名の聴覚障がい学生が、支援室からのサービスを受けています。
学生は、授業形態など各自の状況に応じて、ノートテイク(通訳)、ノートテイク(記録)、手話通訳の中から適切なサービスを利用しています。また、それぞれの支援サービスを併用することも可能です。
それぞれの学生は、授業形態等にあわせて支援方法を組み合わせて講義に参加しています。
通常のノートテイクと違い、普通のノートのようにポイントを絞って書く「NT(記録)」の需要も多くあります。
| 手話通訳 | 手話通訳+NT(記録) | NT | NT(記録) | |
|---|---|---|---|---|
| 学生A | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 学生B | ○ | |||
| 学生C | ○ | ○ | ||
| 学生D | ○ | |||
| 学生E | ○ | |||
| 学生F | ○ | ○ |
(2006年12月現在)
(3)支援者の状況
| 人数 | 合計 | 実稼働率※ | |
|---|---|---|---|
| ノートテイカー(学内者) | 82名 | – | 73% |
| ノートテイカー(学外者) | 7名 | 89名 | 67% |
| 手話通訳者(学内者) | 4名 | – | 75% |
| 手話通訳者(学外者) | 12名 (手話通訳士8名) | 16名 | 78% |
※2006年度前期のみで集計
(2006年12月現在)
用語説明
NT(記録)
1人の支援者が普通のノートのようにキーワードや概念、ポイントを絞って書く方法。一般的なノートテイクのように通訳としてリアルタイムに行うものではない。「聞く」ことに集中したい難聴の学生や、手話通訳を利用するためにノートが取れない学生にとって大きな効果がある。離れて座り、授業後に記録したノートを渡すこともある。
(例)
2.支援者募集の前に
支援者募集の前に、まず以下のことを行い、特に心理的な面についての把握を心がけます。
(1)学生の現況の把握
実際に支援を開始する前に学生と個人面談を行い、以下の事柄を確認します。特に支援サービスを受けることに対する意識や考えなど、心理的な面について把握するように心がけています。可能な限り所属学部の担当者も交えて実施し、情報の共有に努めます。
- コミュニケーション手段
- 聴力の程度
- 高校までどのように授業を受けてきたのか
- 講義保障についてどれほど知っているか
- 自分にはどんなサポートが必要なのか把握しているか
- 現状の問題点
(2)支援方法と活用資源の検討
学生との面談の結果を活かし、様々な支援手段を検討する必要があります。
現状で活用できる資源を整理し、学生のニーズを考慮した上で、どの資源を利用するかを考えます。「ノートテイクありき」ではありません。
ある学生にとって必要な支援手段が利用できない支援体制では、その学生にとっては支援がないのと同じだからです。
聴覚障がい学生側の変化(例えば手話の習得や情報保障に対する意識の変化)によって必要な支援方法・ニーズは変化することもあるので、柔軟に対応できるようにしています。
3.支援者の募集
(1)募集方法
募集方法には以下のようなものがあります。
- 学内のポータルサイト
- 各箇所での掲示や各箇所HPへの掲載
- ボランティアセンターメーリングリスト
- 連携大学へのPR
- クチコミ
- 教員からの紹介
最近はクチコミでの参加も多くなりました。活動中のノートテイカーが友達を呼んでくるという例が増えています。また語学などの専門性を要する講義では教員に依頼をして、大学院生を紹介してもらう場合もあります。
(2)必要人数の設定
募集にあたってあらかじめ目標とする募集人数を設定します。
空き時間が合わないなどの理由から、講座参加者全員が活動できるとは限りません。
また支援者の欠席などに対応するためにも、多くの支援者の登録が必要です。
ここで設定した目標人数が、募集方法や講座の実施回数・時間等を検討する際に重要な判断材料となります。
例えば、13コマにノートテイクが必要な場合、約34人の支援者が必要ということになります。(下記計算式参照)これは、支援者の実働率を75%と想定した場合です。
1コマ2名 × 13コマ ÷ (想定実働率75%) = 約34人必要
4.養成講座の開催
養成講座の開催にあたって、以下について検討する必要があります。
講師
早稲田大学では、支援室のコーディネーターが講師を務めています。できる限り健聴者と聴覚障がい者の2人体制で指導するよう調整し、ノートテイクをする立場と受ける立場の双方から指導できるようにしています。
募集方法
実施時期および時間帯
学期開始直後を基本に、必要に応じて随時実施しています。
学生が集まりやすいように、90分単位で多数設定し、基本的に3コマ分を入門講座にあてます。
一般的に外部講師に依頼する場合は、入門講座として計10時間程度の内容で実施する場合が多いと思いますが、本学では常勤のコーディネーターが日常的にケアできるため、必要最低限の内容を盛り込んで3コマとしました。
入門講座で一定以上の技量を持つノートテイカーを確保することが、日常のコーディネートのしやすさや、ノートテイカーの定着率などに大きく影響するため、力を入れて行っています。
例:「早稲田大学の養成スケジュール」
| 初心者対象 | 経験者対象 研修会 | パソコン通訳 | 談会 | |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | フォローアップ 講座 120分(5回設定) | |||
| 4月 | 入門講座 90分×3コマ 4日間設定 | ↓ | ||
| 5月 | ↓ | 講座 4時間 | ||
| 6月 | 研修会 90分 4回設定 | |||
| 7月 | 研修会 90分 4回設定 | 1対1で個別面談 | ||
| 8月 | ↓ | |||
| 9月 | 復習講座 90分 3回設定 | |||
| 10月 | 入門講座 90分×3コマ 4日間設定 | 講座 1回120分 月1回3ヶ月コース | ||
| 11月 | ↓ 入門講座 90分×3コマ 6日間設定 |
↓ | ||
| 12月 | ↓ | ↓ |
5.カリキュラム例
何を身につけさせたいのか明確にした上でカリキュラムを組みます。その時点での必要性に応じた内容を行うことが重要です。特に経験者を対象とする研修会の場合は、内容を熟考する必要があります。
6.支援者の登録
養成講座を最後まで受講した人には登録書を記入してもらいます。支援者の得意分野、履修済外国語科目、活動可能時間帯、活動可能キャンパス、週間活動可能日数などを把握しておくと後でコーディネートしやすくなります。
→早稲田大学支援者登録書(学内学生用)
時限が合わない等の理由でノートテイクに入れない人も含め、支援者に対するケアを考慮しながら支援体制を運営するよう心がけています。
- ニュースレターの発行
- ノートテイク現場見学
- 研修会の定期的開催
- 手話講座の定期的開催
- 懇談会の開催
- ビデオ文字起こしの協力
活動開始後も可能な限り現場を把握しておくようにしています。
初回のノートテイク終了時には、メールで感想を聞いています。
月々の活動報告書をもとに、必要があれば各箇所や教員と連係して状況の改善に努めます。コーディネーターが授業を見に行くこともあります。
→早稲田大学支援者活動報告書
講師:早稲田大学障がい学生支援室コーディネーター 岡田孝和氏(所属・肩書き及び掲載情報はすべて2006年度時点)